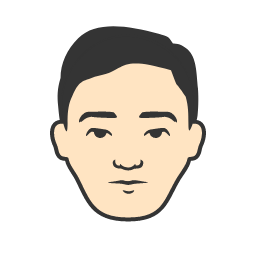
公開2週目。月曜朝8:45の回。10人以上はいました。広めの部屋で映画に没入する
結論
4人の女優の美しさを堪能し、当時の長崎の再現を懐かしく楽しむことができる佳編。オススメ!
概要・あらすじ
2017年にノーベル文学賞を受賞し、「日の名残り」「わたしを離さないで」など、映画化作品でも非常に高い評価を受ける作家カズオ・イシグロが、1982年に綴り、王立文学協会賞を受賞した長編小説デビュー作品「遠い山なみの光」。自身の出生地長崎を舞台として繰り広げられる本作は、戦後間もない1950年代の長崎、そして1980年代のイギリスという、時代と場所を超えて交錯する“記憶”の秘密を紐解いていくヒューマンミステリー。
公式サイトより引用
日本人の母とイギリス人の父を持ち、大学を中退して作家を目指すニキ。彼女は、戦後長崎から渡英してきた母悦子の半生を作品にしたいと考える。娘に乞われ、口を閉ざしてきた過去の記憶を語り始める悦子。それは、戦後復興期の活気溢れる長崎で出会った、佐知子という女性とその幼い娘と過ごしたひと夏の思い出だった。初めて聞く母の話に心揺さぶられるニキ。だが、何かがおかしい。彼女は悦子の語る物語に秘められた<嘘>に気付き始め、やがて思いがけない真実にたどり着く──。
同上
感想
映画を観た後、長く積読だった原作文庫本を読み始めました。映画との最大の特徴的違いは、映画ではキャストの多くが方言(長崎弁等)を使うこと。イギリスでの悦子が全編英語だということです。小説上はすべて標準の日本語での表記となります。これは映画の立体感を感じさせます。
じげもん(長崎人)の私が聞いても広瀬・柴田の長崎弁は見事でした。特にうどん屋店主の柴田の忙しないしゃべり方は、ああこんなおばしゃま(おばさん)がいたいたと幼い頃の近所のおばさんを彷彿とさせました。

吉田の英語もなんの違和感も無く入ってきました。役者さんはすごいなと感じさせます。イギリスの郊外の様子を私は知るよしもないので、映画のイギリスの風景がどれほどリアルかはわかりませんが、小説ではそれ以上に場面の違い(イギリスか長崎か)はわかりません。映画の大きな優位性です。
さて話題を映画に集中させていきましょう。1952年の長崎は私が生まれる10年ほど前のことなのですが、例えば稲佐山から望む長崎港の姿は「ああこんなだった」とその再現度に感心します。
アパートのキッチンからの配膳口がおしゃれだと話題になりましたが、私はあまり見たことがないですね。私が育った町にはアパートは無く、長屋が多かったです。平屋の長屋に住んでいる友だちはいっぱいいました。そこには配膳口などなかったです。
映画の中ではこの配膳口は多用されず、緒方へのお弁当を差し出す1回だけのようでした。しかしただ1度だけだからこそ印象に残ります。配膳口から悦子の手と風呂敷に包まれた弁当だけが画面に映ることで緒方との完全に親しくなれない関係のようなものが感じられます。

この緒方というキャラクターは、復興に向かう50年代の日本において、米国が導入した民主主義の波の中において異質なものとして描かれています。教師として戦中に子どもたちに指導してきたことは決して間違っていなかったと確信している。自分が成してきたことは彼の生きる柱であり、それを簡単に否定することは難しいのでしょう。
朝ドラ「あんぱん」の中で主人公「のぶ」がすっぱりと戦中の自分の行ってきた教育を捨ててしまうのと対照的です。どちらがよいというような問題ではなく、どちらのタイプの人もいたことだと思います。
緒方は自分の行ってきたことに確信をもっていた。ゆえに、息子の二郎が出征の時にも大きな声で喜びを表した。息子が戦争に行くときでさえです。その生き方が二郎に嫌われる要因であっても、緒方には簡単に反省できない教育に対する理念をもっている。
多くの私たち戦争を知らない子どもたちは、GHQの残した法律のもと、我が国の歴史をして自虐的な反省的なそれを教えられてきました。真実の歴史は本当は何なのか今ですらわからない。タイムマシンで実際に見に行くしかない。今は無理ですね。

さて本作は、ある女性とその娘との会話の物語であるのに、4人の女優が美を競うようにスクリーンに登場するのが実におもしろいですね。大画面で美しい女性の姿を見るのは私にとって映画を観る理由の多くの%を占める要素です。「キネマ旬報」誌に「カラダが目当て」という連載がありますが、多くの特に男性はうなずく人は多いでしょう。

「国宝」の大ヒットも多くの女性が横浜流星と吉沢亮の美を観に行くためではないかと思います。私はあまり興味なしですが。
映画の前半は原作をかなり忠実に再現していると思います。石川監督の「ある男」でもそれは感じました。本作では例えば散歩する悦子とニキが近所のおばさんと対話する部分。ほぼそのまま原作を再現していると感じました。

本作の謎については予測はついてしまいます。被爆女性への二郎の差別の結果であることは間違いないでしょう。被爆したことを偽っていた悦子にも責任の一端はあるかもしれませんが、戦争が終わってもこのような不幸を招くのが原爆の恐ろしさであることが訴えられていると思います。
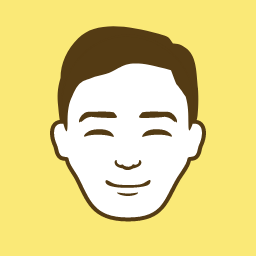
4人の美女を堪能しながら、当時の長崎の再現度にも感心させられる作品に仕上がっています。オススメです。ぜひ劇場の大画面でご覧ください。
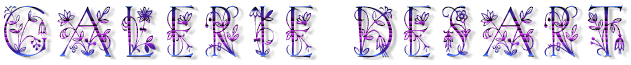

コメント