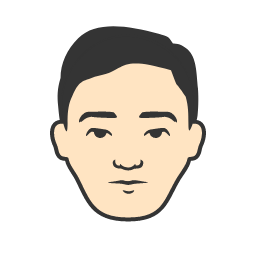
いろいろな形態のアンサンブルに参加しますが、弦楽四重奏のバランスの良さは格別。リラックスして合奏を楽しめます。
結論
この演奏形式の起源からハイドン・モーツアルト・ベートーベンを深掘り。バルトークから12音派まで言及し、全体を俯瞰するのに好著。譜例はあまり役にたたないかな。
概要
二つのヴァイオリンとヴィオラ、チェロによる弦楽四重奏は、室内楽曲のなかでも最も純粋な音楽形式である。その起源から説き起こし、今日までの歴史と、四重奏団の特質も紹介。
amazonより引用
こちらの本の内容は、時代の流れを追いながら、大まかに3つの章に分けられています。
各章の前には必ず「序」が置かれていて、「序」の中で筆者なりの問いをいくつか立てた後、それに対して章の中で答えを導いていく、バカロレア(仏)の哲学の試験のような構成です。
ネットより引用
感想
本書では弦楽四重奏の起源を「ヘンリー8世やエリザベス1世時代にイギリスで行われていた『ヴィオール合奏』に相当するもの」と記されています。
その特徴は「音色の同一性」「各楽器の平等性」「絶え間ない楽器の対話」です。そのもとで精緻きわまりないポリフォニーが作曲スタイルだったようです。非常に魅力的です。
当時の作曲者はメイスやフェラボスコなど今では聞いたことが無い名前ばかりです。当時の楽譜が残っているのでしょうか?調べてみたいと思います。

柔らかい音響をもつヴィオール合奏は貴族やブルジョワの室内で演奏されていました。野外ではその精緻で柔らかい響きは実現できない。野外での祝祭などでは管楽器が力を発揮します。
先日響きが悪く、しかも床が絨毯状になっている会場でオーケストラ演奏を聴きましたが、フルートとオーボエたった2人のオブリガードに、何十人ものバイオリンの旋律が負けてしまうという事態を目の当たりにしました。
弦楽四重奏の原初から説き起こした本書は、その後ハイドン、モーツアルトの多数の作品を分析することに進みます。この二人の作曲家の曲を私たちアマチュア弦楽四重奏団はよく取り上げ演奏します。体感的には第1バイオリンに技術的ウェイトが高く、名人芸1人とその伴奏的な3人という感じです。
しかしそれはベートーベンの中期以降で完全に変化してしまいます。ベートーベンの作品18の6曲までは何とか演奏可能ですが、ラズモフスキーからはもうなかなか歯が立たなくなってきます。
本書はこのベートーベンの16曲を詳しく分析していきます。譜例も多く掲載されていますが、譜例と文章の関係が読者にわかりやすく示されているかといえば、そうでないと思います。専門性が低い私などには理解しにくい部分でした。残念。
その後、シューマン・ブラームスのドイツ系からドボルザーク・スメタナなどスラブ系、ボロディンなどロシア系までざっと紹介されます。メンデルスゾーンは少なかった気がしました。

ドビュッシーとラベルの革命的な2曲については十分な紙幅をさいて説明されます。この2曲は多くの弦楽四重奏団がカップリングで録音しており、名演奏も多数です。以前に小澤征爾の音楽塾で弦楽四重奏を育てるプログラムがあり、その成果発表会のコンサートを生で聴く機会がありました。
そこで演奏された若い弦楽四重奏団のドビュッシーの3楽章のビオラの深い音に大きく感動したことを覚えています。たぶん韓国の女性プレイヤーだったと思います。ドビュッシーのたった1曲の弦楽四重奏は弦楽四重奏史の至宝だと思います。
コンサートの最後には出場した全員が舞台に並び、そこに小澤登場。ベートーベンの作品の緩徐楽章を指揮したのでした。今思えば貴重な場面に立ち会うことができて嬉しく思います。
ベートーベン同様、その生涯弦楽四重奏を作り続けた作曲家にハンガリーのバルトークがいます。バルトークが残した6曲についてかなり紙幅をさいて分析しています。著者はバルトークの弦楽四重奏曲を「同時代の作曲家の作品と完全に断絶して」おり「何とも形容できないリズムや味わい深い生命感が発散」すると大いに評価しています。
バルトークの巨大な6曲は人類の宝といってもいいのですが、「クワルテットのたのしみ」(アカデミア)で言及されているように「アマチュアは手を出すべからず」のものですので、我らアマチュアカルテットはそのお宝を楽器で表現するのことは難しい。
なのに以前果敢に第1番の1楽章をやったことがあります。第1バイオリンから静かに始まるフーガでバルトークの音楽に少し触れることができました。発表会にかけるという暴挙もやりました。若かったなあ。
最後に12音技法の作品を挙げて本は終末に向かいますが、残念なのはショスタコーヴィチの作品が非常に薄く、彼の新たな工夫は楽章の性格を「序曲」「ワルツ」「変奏曲」等のようにしたという表記だけです。これはあまりに分析がされてなさすぎるように思います。
活躍する世界の弦楽四重奏団についてもざっと紹介するにとどまっています。弦楽四重奏団とその演奏に関しては別の書籍を探してみたいと思います。近著はあまりないみたいですが・・・。
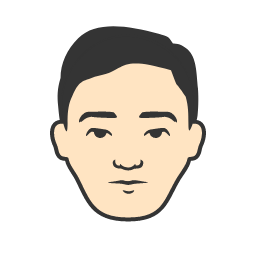
巻末の関係書籍を図書館で検索してみましたが、1冊も引っかかりませんでした。地方図書館の悲しいところです。メルカリで1冊見つけて購入しました。この夏は弦楽四重奏掘ってみます。
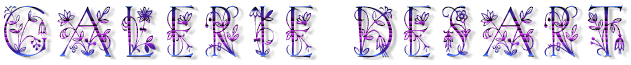

コメント