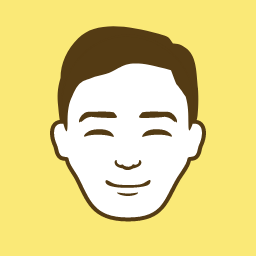
冒頭の様々なボレロびっくりしました。どれだけ世界中に愛されている曲でしょう。
結論
美しい映像と音楽の上に浮かび上がる悲しみが心にしみる。
概要・あらすじ
時代と国境を越え愛され続ける名曲「ボレロ」の誕生秘話を描く音楽映画。『夜明けの祈り』のアンヌ・フォンテーヌがメガホンをとり、『黒いスーツを着た男』のラファエル・ペルソナが主演を務める。また、『ベル・エポックでもう一度』のドリヤ・ティリエ、『バルバラ~セーヌの黒いバラ~』のジャンヌ・バリバール、『ダリダ~あまい囁き~』のヴァンサン・ペレーズらが脇を固める。
ネットより引用
深刻なスランプに苦しめられている作曲家モーリス・ラヴェルのもとに、ダンサーのイダ・ルビンシュタインからバレエの音楽の依頼が舞い込む。一音も書くことができないラヴェルは、失ったひらめきを追い求めるように人生のページをめくっていく。戦争の痛みや叶わない愛、最愛の母との別れなど、引き裂かれた魂に深く潜り、ラヴェルはすべてを注ぎ込んで傑作「ボレロ」を作り上げる。
同上
感想
冒頭のタイトルバック、まさに様々なジャンルの音楽(ジャズ・ロック・フォーク・ラテン・アフリカン・スパニッシュetc)で奏でられる「ボレロ」の映像と音楽に仰天。この曲の人の心をつかんで離さない魅力が頭から提示されます。
このボレロの誕生秘話が映画の主筋ですが、その裏に流れるラヴェルの悲しみが背骨になっています。
親友の妹ミシアとたぶん相思相愛ながら、一線を越えないラヴェル。そのもやもやを紛らわすように娼館に向かうも、何もせず娼婦にミシアの忘れた手袋をつけさせるラヴェル。
男性としての機能不全があることが伺い知れます。女性を愛しながら交わることができないラヴェルは、音楽に身をささげた修道士ともいえるでしょうか。
主人公たちをかなりの接写で切り取り、フォーカスがあったり合わなかったり。それが非常に美しい映像となっています。特にミシアの表情の美しさ、肌の透明感は官能的ですらあります。

ふたりの腹立たしくなるほどの揺れ動く関係と対峙するかのように、きっぱりとした人間として描かれるのがダンサーのイダです。しかし彼女も芸術を追い求める芸術家であることはまちがいありません。映画の中でヴィランとなる彼女はなくてはならない存在だと思います。

アメリカ各地のツアーの様子を、「亡き王女のためのパヴァーヌ」の演奏で、ささっと表現されます。アメリカでの重要ポイントがジャズとの出逢いとでもいうように、ジャズクラブでのシーンは濃密で官能的。黒人ボーカリストの魅力がほとばしっています。

ここでのジャズとの出逢いが、ピアノ協奏曲ト長調や左手のためのピアノ協奏曲に結実するのでしょう。映画ではマルグリット・ロンがト長調の2楽章を弾くシーンが出ます。この曲はマグリットに献呈され、ラヴェルはマルグリットと共にこの曲を携えて、ヨーロッパ中を演奏旅行したようです。二人は深い友情でつながっていることは映画の中でも伺えます。
それにしても、映画の間中ラヴェルはたばこをふかしています。相当なヘヴィースモーカーです。
弦楽四重奏を批評家が「ドビュッシーの亜流」と評していましたが、ドビュッシー自身はラヴェルの四重奏を高く評価していたようです。
このラヴェルの宿敵のような批評家は、ドビュッシーには情感がありラヴェルにはそれがないと断じます。それは私は個人的に少し同意で、ドビュッシーの音楽の方がどうしても好きですね。
映画の冒頭は機械音がすさまじい工場でラヴェルとレダが出会うところから始まります。ラヴェルは工場の音を「未来のシンフォニーだ」と称賛します。ラヴェルはこの機械的な音の重なりを受け入れ憧れてさえいるように見えます。

そんなラヴェルの紡ぎ出す音楽が機械的な面があるのは当然のことのような気もします。
映画では主人公達を始めとして美しいものがひしめいていますが、その一つがラヴェルが苦しみながら作曲を行う仕事場から望む海の風景です。寒々とした海に島がぽつんぽつんとあり、絵画的に美しい。
コンサートホール、娼館も美しく撮影されていて映画的な喜びに満ちています。
音楽はもちろんラヴェルの音楽が使われるわけですが、コンサートでの演奏より私はラヴェルとミシアが連弾する「マメール・ロア」が心に残りました。二人の思いがこの妖精の音楽を夢のようにはかなく美しくしていたように思います。
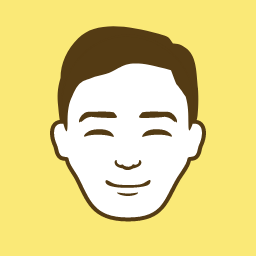
女性監督ならではの美しい映像とラヴェルの音楽に酔いしれながらも、彼の悲しみが浮き立つ佳編。ぜひ御覧ください。

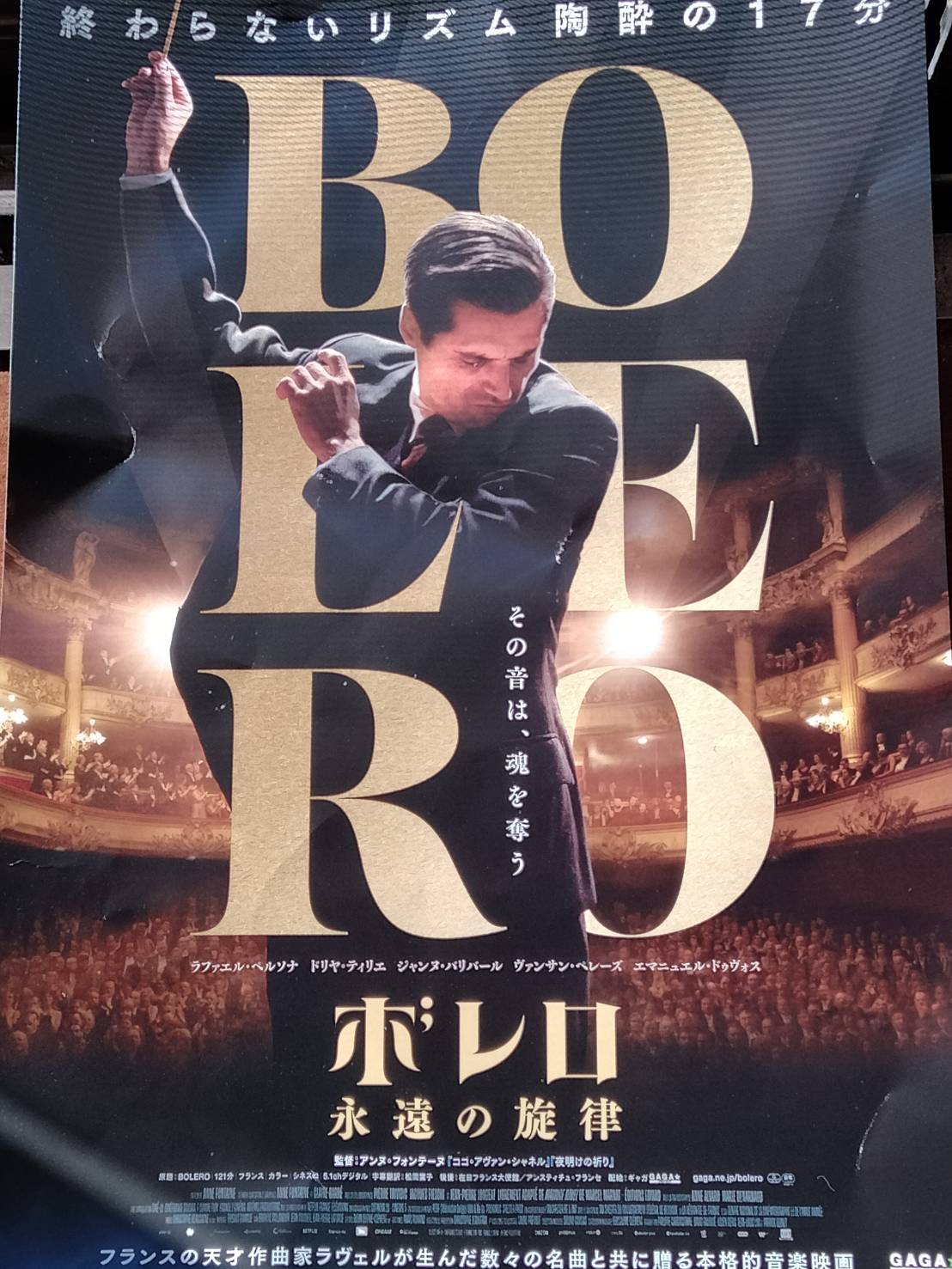
コメント