久し振りのプロのオーケストラ演奏会に行ってきました。長崎OMURA室内合奏団の定期演奏会です。
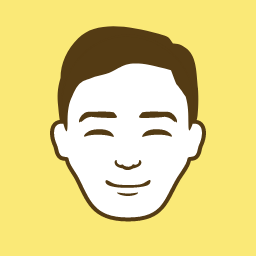
弦楽器を中心としたプログラムでした。「20世紀の音楽」がテーマで、少し難しい曲もありましたが、さすがに本職です。緻密なアンサンブルを楽しませてくれました。
プレコンサート
開演は19時からでしたが、私は早くに会場に着き、文庫本のミステリーを読んでいたのですが、16時45分くらいに5人のプレーヤーが舞台に登場しました。木管五重奏(フルート、オーボエ、ファゴット、ホルン、クラリネット)の陣容です。
どうやらプレコンサートが始まりそうです。これは早く席についていてラッキーです。

曲は最後に紹介がありました。ジャン=ミシェル・ダマーズというフランスの作曲家の「木管五重奏のための17の変奏曲」からでした。このダマーズという人は1928年生まれの人で、2013年に亡くなっていますから、現代の人ですね。曲は調性がはっきりしていて、とても聴きやすい曲でした。
演奏も快活で、複雑なリズムの重なりを見事に演奏されていて楽しかったです。まだまだ知らない曲はいっぱいあるのですね。フランスのおしゃれな気分の音楽に、演奏会への期待が高まります。プレコンサートっていいですね。毎回あるのでしょうか?今回は管楽器の出番が少ないせいもあるのでしょうかね?
エルガー
気分が上がってきたところで、いよいよ本編のスタートです。
最初の曲は、英国の名作曲家エルガーの「序奏とアレグロ 作品47」です。これは弦楽器だけの弦楽合奏となります。エルガーは「愛のあいさつ」や「威風堂々第1番」が有名ですね。私は、今回の「序奏とアレグロ」は初めて聴きます。
「序奏とアレグロ」はエルガーが人気絶頂だった1905年に、ロンドン交響楽団の委嘱を受けて書かれた作品です。ロンドン交響楽団は前年の1904年に結成されたのですね。意外と歴史は浅いですね。といっても、百年以上はたつわけですが。
この曲は弦楽合奏に独立した弦楽四重奏が加わる形で、バロック時代の合奏協奏曲を思わせる編成とのことです。
冒頭から重厚な弦楽器の響きが満ちてきます。冒頭の合図はビオラのトップの方がとられたようでした。この人はゲストプレーヤーの坂口弦太郎さんです。NHK交響楽団の人ですね。この人の美しい音はとてもよく聴こえてきました。すごいです。

一番内側の4人が独立の弦楽四重奏ですね。コンサートマスターとその後ろの男性との間が少し空いているのでよくわかります。この4人のプレーはやはり凄いの一言ですね。特に第2バイオリンの女性の音は太く大きくよく鳴っているように思えました。
この弦楽四重奏と弦楽合奏が、ときに一緒にときに対比的に演奏が繰り広げられ、とてもスリリングで楽しく聴かせてもらいました。ひとついい曲を教えてもらった気がします。
ラヴェル
2曲目で管楽器の登場です。ひな壇の二段目三段目に乗ります。トロンボーンやチューバなどはなく、その代わりに舞台下手にハープが登場します。打楽器もありませんね。室内合奏団が演奏可能な楽器編成とわかります。
組曲「クープランの墓」は、もともとはピアノの為に書かれた組曲の中から、ピアノの技巧面が全面に出される「トッカータ」と中間部の「フーガ」を除いた四曲をラヴェル自身が管弦楽のために編曲したものです。
「クープランの墓」とは不思議な題名ですが、これはクープランに代表されるバロック音楽の時代の形式を借りた、第一次世界大戦で犠牲になったラヴェルの知人たちを忍ぶ追悼または追想の曲であるためです。
この曲は私は大好きで、よく聴いていますが、生演奏は初めてかも知れません。わくわくします。曲は管楽器の水が流れるようなわき出してくるような音に始まって、すぐに弦楽器が加わります。この曲は管楽器は特に高度な技術が必要とのことですが、見事に演奏されています。
弦楽器の様々な奏法も聴くことができ興味深いです。特にハーモニクスの笛のように高い音が印象的ですね。
また、ハープが効果的に活躍するのも実にすてきです。どの曲かのエンディングに風が吹き抜けるようにハープが鳴って、木管楽器のトレモロで終わるのはとても爽やかで心に残ります。
普段は高らかにファンファーレを吹き鳴らすトランペットが、アンサンブルの中にきちんとはまって、なおかつ独特の金管楽器の音のスパイスが効くのも見事な編曲だし、もちろんトランペットの演奏も素晴らしかったです。いやあ名曲です。フランスの香りを十分に味わうことができました。
バルトーク

15分間の休憩の後には、舞台のひな壇の譜面台が片付けられ、再び弦楽合奏での演奏となります。曲はバルトークの「弦楽のためのディベルティメント」。
この曲が作曲されたのは1939年ですから、第二次世界大戦中です。前年にオーストリアがナチスドイツに併合されます。ユダヤ人の妻をもつバルトークは民族音楽の研究を続けるために、アメリカへの移住を考えていたそうです。民族音楽の研究を戦争に邪魔されたくなったのでしょう。
「ディベルティメント」はおもに18世紀後半に盛んに書かれた多楽章の器楽曲です。モーツアルトやハイドンのものが有名ですね。日本語では嬉遊曲(喜遊曲、きゆうきょく)とも訳され、もともとは「楽しい、面白い、気晴らし」的な音楽です。
バルトークの「ディベルティメント」も、3楽章の前後は闊達な音楽ですが、聴いて即「楽しい」というのとは異なります。バルトークの音楽は、長調か短調かどっちかな?という感じです。
さらに、2楽章はゆっくりした中にとても難しい感じを秘めています。非常に小さい音で、低音楽器から半音階で重なっていき、不気味です。でもホラー映画の劇伴奏などとは違って、明るい高音楽器も重なってきて、調は判然としません。陳腐かも知れませんが、しのびよる戦争の不安という面はあるとは思います。
何を感じるかが聴く者にゆだねられている。それは芸術の普遍性ですが、リストに始まる「交響詩」のような表題的な世界と違う、純音楽世界に戻ったような感じがしました。
終楽章は、ソロ楽器と弦楽合奏が交互に出たり、弦楽合奏群も2つに分かれていたりと、構成のおもしろさをたっぷり感じさせてもらいました。グリッサンドや弦を上に引っ張って放すことで弦が指板に当たって「バチン」という打楽器的な音をさせるバルトークピチカート(これ1楽章かな)などの特殊奏法も出てきて面白かったですね。
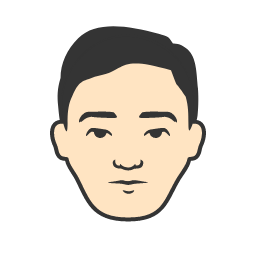
全体に弦楽器の音色を十分に感じることができてよかったです。でも、会場にもっと残響音があればよかったと思いました。響きにくい会場のため、弦楽器の直接的な音が強調されてしまいました。また、コンサートマスターの方と他の第1バイオリンの方との一体感がもっとあればと感じました。とまれ、コロナのためにコンサートがほとんど無かった時を越えて、これからどんどん演奏会が行われ、私たちがもっと音楽の喜びを享受できるようになって欲しいと願います。そのためにも、地元のオーケストラを応援したいと思います。


コメント